|
ンフラ整備も同時に推進していくことを課題としたい。
最後に、ご多忙の折、今回の訪問を快くお引き受けいただいた青木先生と市大のスタッフの皆様にこの場を借りて感謝申し上げたい。
|
獨協大学外国語教育研究所(埼玉県草加市)
1981年設立。6つのLL教室の他にAVライブラリー、AV学習室、PC語学自習室がある。スタッフは、所長、視聴覚教育主査と研究員7名、職員9名。獨協大学の外国語学部には、ドイツ語学科、英語学科、フランス語学科、言語文化学科がある。他に経済学部、法学部。 |
「語学センターを見学して」
広島工業大学電子・光システム工学科助教授
酒見 紀成
学生は受け身なだけでいられないCALL教室
「うらやましい」
これが市立大学の語学センターを見学した私たちの率直な感想ではなかったかと思う。でも、市立大学には国際学部があるので当然かと思い直した。LL教室が3つと自習室が1つ、スタジオ・編集室に豊富な教材。しかも、4つの教室のうち3つは最新のCALL教室だ。とくに感心したのは、インテンシブのような独自に開発された様々な学習プログラムである。
広島工業大学には17年前に作られたLL教室(1)が1つと、6年前に作られたMM教室(2)が1つあるだけ。それらも今はあまり利用されていない(もっとも、ある非常勤の先生は中国語の授業をPC教室(3)で行っていらっしゃるが)。そこで、私たち英語担当者はそれらの教室をCALL教室に変えるよう大学に要望しているところである。では、なぜCALLか?それはコンピュータが安価になったこと以外に、コンピュータを利用した新しいシステムや様々な学習ソフトが入手できるようになったことが一つ。もっと重要なことは、従来の授業形態ではどうしても学生が受動的になりがちだということだ。CALL教室では、ただ座って聞いているだけというわけにはいかない。もう一つの利点は、PC教室を使われている先生によれば、個々の学生の質問に答えてやる時間が多くなることである。
新たなWeb教材作成を目標に
しかし、CALL教室を使った授業がすぐに従来型の授業に取って代わるとは思われない。CALL教室の数、適切な教材の入手、教員のシステムへの不慣れ等の問題がある |
からだ。おそらく必修科目ではなく、選択科目の一部で、CALLに関心のある教員が始めることになるだろう。
諸般の事情から、工大にCALL教室が設置されるのは平成16年度になりそうなので、それまでは助走期間と思い、CALLシステムや教材について勉強し、できれば、新たなWeb教材を作成したいと思っている。また、当面はPC教室で市販のCAI(4)ソフト(英検やTOEIC対策の)を使うつもりである。そうすればPC教室の限界、CALL教室の長所なども分かってくるものと期待している。
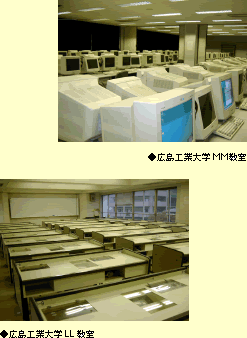
注:
(1) LL教室・・・1985年に導入。現在17年経過。中国松下で70ブース。現在、リプレイスを検討中
(2) MM教室・・・マルチメディア教室。平成8年に自学自習用として導入されており、CALL機能は全く入っていない。現在のLL教室とあわせて、CALL機能を導入したマルチメディア教室へリプレイスを検討中。
(3) PC教室・・・情報基礎教育のための教室。PC1(84台)、PC2(84台)、PC3(80台)設置。来年、秋にリプレイスを予定。
(4) CAI・・・Computer Assisted Instruction=コンピュータを用いた学習システム。
|
広島工業大学(広島市佐伯区)
理系の大学のため、外国語関連の学部はなく、工学部、環境学部がある。 |
|