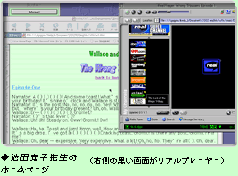|
恋の文学トンネルズ2
イーデン、エデン、楽園
やめておけといわれてやめられるものならいい。愛することをやめられないのは人の宿命なのだ。色恋はやめられない? 始末におえぬ、反理性的なもの?
だが、理性だの寛容だのという一方の人間の美徳がこの葛藤の波風を鎮めうることもある。
愛のない人は人間ではない。ひとでなしめ。愛なしには生きられないが、愛のみ、それだけに生きてしまう人も人でないんじゃないか。人間は状況をこちらから変えていくことも可能なのだ。「時代背景」という言葉が示唆するように、メインは時代を背にして前景を生きる、背景をも変えられる個々の人間の姿なのだ。
さて、南部の人種差別を背景にしたピート・ハミル『愛しい人』(高見浩訳、河出文庫、92年10月刊)だ。
1952年の大晦日、バスでフロリダ州ペンサコーラ海軍基地へ向かう17歳のマイケル。朝鮮戦争下、彼は陸上勤務の水兵として入隊するのだ。「もう十分に大人」だ。バス後部の座席は暗くてよく見えない。そこに坐るのは「ニグロ」(当時はまだ、そう言っていた。キング牧師がバス・ボイコット運動を始めるのは55年12月)だ。隣席に黒い髪、黒い瞳の、のちに熱愛関係となる女性が坐った。
2.5ドルのシャツと6ドルのチノ・パンツを買ったシアーズの女性下着売り場のカウンターに、その大晦日のバスの女がいた。胸の名札にイーデン・サンタナと
|
ある。声に出せば「まろやかにうねる」。「イーデン。エデン。楽園のような響き」。ボートを漕ぐ。「オールがイーデンという音を発するような気がする。イーデン、イーデン」。
彼女の家はトレーラーだ。貸トレーラー。家賃月35ドル。「花の香りの漂う、雨に閉じ込められた、あの小さなトレーラーの中で」美術家志望のマイケルは裸のサンタナを木炭で描いた。
18歳の水兵、マイケルは国吉やベン・シャーンの画業を知りスターリンの死を聞き、車の運転を教わり音楽の魅力に触れ、そして何より愛の官能を知る。
北上次郎は「いちばん哀しく切ない恋愛小説は何か」と問うてこの小説を挙げるほどイカレタくちなのだ。「官能=いのちの燃焼を青春小説のかたちを借りて鮮やかに描いた傑作」、「読みながら自分の若き日のことを何度も何度も考えていた。そういう力に満ちた書」と絶讃する(『別れのあとさき』毎日、『新刊めったくたガイド大全』角川文庫)。
青春小説は年輩者の哀惜の文学でもある。然り。ハミルのできすぎた麗しい短編「黄色いハンカチ」(『ニューヨーク・スケッチブック』河出文庫)は若者たちと年老いた前科者との色鮮やかな交流話(やはりバスの中のことだ)。人生の経験に富む者と未熟な者の、心がひとつになる美しき一瞬。
 冒頭のやめられるか否かの議論のついでに言えば、やめさせたいのは全ての国で若者を苦しめている、徴兵制である。 冒頭のやめられるか否かの議論のついでに言えば、やめさせたいのは全ての国で若者を苦しめている、徴兵制である。
(zero-zero愛)
|