 「インテンシブプログラムを正式英語科目にするにあたって」 受講希望者殺到プログラムの今まで、そしてこれから 国際学部教授 青木 信之 |
| 広島市立大学語学センター Newsletter No.15 (2002.5.31) |
p.1 |
 「インテンシブプログラムを正式英語科目にするにあたって」 受講希望者殺到プログラムの今まで、そしてこれから 国際学部教授 青木 信之 |
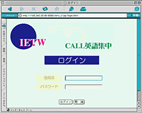 国際学部の渡辺智恵講師と開発してきたIETW(Intensive English
Training on the Web)、通称インテンシブプログラム(以下、インテンシブ)が正式の授業となった。この4月から、国際学部1年生の「CALL英語集中」という必修科目として、そして情報科学部、芸術学部1年生には「CALL英語総合」という選択科目として、英語の単位が認定される正式の科目となった。 国際学部の渡辺智恵講師と開発してきたIETW(Intensive English
Training on the Web)、通称インテンシブプログラム(以下、インテンシブ)が正式の授業となった。この4月から、国際学部1年生の「CALL英語集中」という必修科目として、そして情報科学部、芸術学部1年生には「CALL英語総合」という選択科目として、英語の単位が認定される正式の科目となった。 このインテンシブの計画は5年前に始まった。絶対的な学習量が不足する大学の英語授業において、なんとか学習量を補えないか、しかも人的、予算的手当が不要な形でできないかと考えたことが始まりであった。こういった経緯は青木・渡辺(2000)※注に書いたが、簡単に述べると、外国語の学習はスポーツと似ているところがあり、コーチがつきっきりで指導すべき知識や技能の学習という側面と、コーチがいなくてもひたすら球を打つような訓練の側面がある。しかし、その両方を週に2、3回の授業で教師が行うには時間的に無理があるし、また無駄である。教師にはできるだけ、その教師でないとできないことを教えてもらい、あとは学生だけで行える訓練の場、効率的に訓練を施せる場を作ることはできないかと考えたのである。その一つの試みとして、語学センターのCALL教室を使い、コンピュータ上で問題を提示し、それに対する音声をテープで聞き解答するといったかなり原始的なプログラムを1ヶ月行った。当時は予算がなかっただけでなく、コンピュータの処理能力やまたネットワークの速度などさまざまな問題があり、音声や画像も一緒にネットワークで配信し、かつ即フィードバックを与えるということができなかったのである。また、プログラムの効果を測るための事前事後テストも、現在のような正式なTOEICではなく、模擬テストをコピーしたものを用いた。しかし、この原始的なプログラムは、徹底的 |
な英語学習の場を望んでいた学生たちに好評で、しかも事後の模擬テストではかなり成績が上がっていたのである。 そこで、翌年から正式に予算を申請し、コンピュータネットワークを利用したプログラムとして本格的な開発を開始した。具体的には、つぎのようなことを念頭において開発を行った。 ・コンピュータで学習するのにより適した受容技能、つまりリーディングとリスニングに特化した学習プログラムを開発する。 ・苦手な文法項目を克服するようなミニ文法プログラムを開発する。 ・効果的な教材提示の方法を考える。 ・効果的な解答フィードバックの方法を考える。 ・プログラムの側だけでなく、学習者側の効果的な取り組みのあり方を考える。 ・学習効果を客観的に把握する。 ・市立大の学生にとっての適切な教材レベルを把握する。 他にも目的はあったが、主にこのような点を考えて開発を行った。またその時期に、情報処理センターや語学センターの機器更新があり、コンピュータの処理速度やネットワークの速度が飛躍的に改善された。このことにより、教材の提示方法やフィードバックの方法などの選択肢がかなり広がったのである。 それから3年間で開発したのは、英文を読み内容把握問題を行う多読形式のリーディングプログラム、英文一つ一つを丁寧に読む精読プログラム、TOEIC形式の問題を解くリスニングプログラム、日本人の多くが苦手とする冠詞の学習プログラム、またTOEIC形式の文法問題プログラムであった。教材提示や解答フィードバックについては、外国語学習や教授に関する理論的研究などをもとに、常に実験群と統制群を設定し、試行錯誤を繰り返した。(→p.4へ続く) |
|
| ←目次ページへ戻る |
|